ビブリオバトル入門《2025》
#3 好きな本を紹介しよう②:第2ラウンド
October 22, 2025
Ⅰ. 授業の感想
授業の感想
ほかの受講生の発表について質問をすることは意外と難しいことだと実感しました。でも、どれだけほかの人が苦し紛れに出した質問であれ自分が発表したときにほかの人からもらった質問によって、どんなところが伝わっていなかったのかや、こういったところを説明するといいのか、といったことがわかり次回の発表についての参考になりました(井上さん)。
今日の授業では、グループでそれぞれおすすめの本を紹介しました。自分が最初に発表しましたので、ちょっと緊張しています。でもなんとか発表できました。正直に言うと、ほかのメンバーの発表はとても素晴らしいです、自分はもっと頑張らないといけないなと感じました。印象的だったのは、みんなが紹介した本がどれも文学的で内容が深かったことで、自分の読書の幅が狭いなと気づかされました。普段はあまり読まないジャンルですが、今度は試しに読んでみたいと思います(谷さん)。
授業の感想
みんなそれぞれ好きなジャンルがあって、自分にも好きなジャンルがあるからどうしても読む本は偏ってしまいがちだけど、ビブリオバトルでは自分が絶対に手に取らないような本の紹介が聞けて面白いと改めて思いました。私はミステリー系が好きなので、トリックが面白かったり劇的な展開があったりする本をどうしても手に取ってしまうけど、今回のビブリオバトルで班の方が紹介していた本がとても穏やかな雰囲気の本で、時間があるときにゆっくりと読んでみたいなと思えるものでした。ビブリオバトルは狭くなってしまいがちな視野を広げてくれて、新しい本の中の新しい考え方などに出会える場なのだと気付かされました(坂田さん)。
初めてのビブリオバトルをしたが、想像以上にグループのみんなの構成の緻密さが高くて驚いた。特に、ある人は自分の好きな本を言う→本の特徴を絞って述べる→選んだ理由を言う→作品内での自分の推しキャラについて熱く語る というように一連の流れがスムーズに楽しく述べられており聞き手側としては、わかりやすくかつ暇な時間がなかったので非常に聞きやすかった。自分の構成にもいくつかの無駄な点や分かりにくい点を、講評を通して気が付いたので修正して次に望みたい。学びのある時間だった(竹田さん)。
授業の感想
今回の授業で初めてビブリオバトルを行い、難しいものだと思っていたが案外楽しくできて良かった。どのようにしたら聴衆の興味を惹きつけることができるのかについて、授業前に考えたこと(本の内容を全て話さないことや、質問をしてみるなど)を行うことができた。また、グループで行う時とクラス全体で行うときのビブリオバトルのやり方は少し違うのではないかと考えた。グループでは一人一人の表情を見て、反応が悪ければ話す順番を変えたり工夫できるが、クラス全体だとそれが出来ないため、一部の人ではなくより多くの人たちの興味を引く内容を考えるやり方が有効ではないかと思った(デルガードさん)。
班の中でも紹介した本のジャンルがさまざまで、自分からは手に取らないような本についても知ることができてよかったです。本には人を感動させるだけではなく、読む前と読んだ後で読者の考え方を変化させたり、新しい考え方に納得できるようにさせたりする力もあるのだと思いました。本の紹介と聞くと本の内容をイメージしますが、作者の意図、自分自身の考え方などについても紹介してみるとより良い紹介ができるようになりそうです(若林さん)。
Ⅱ. グループワーク:好きな本を紹介しよう 第2ラウンド
授業の約束(教員との約束)
この授業はグループワーク中心の授業です。教員一人では授業を作ることができません
- 教員:学びの空間設計者
- 受講生:コンテンツ制作者
皆さんも授業を作るメンバーとして、以下の3つを心がけて下さい
- 元気に毎回出席する(ただし無理は禁物)
- グループワークには積極的に参加する
- 提出物はちゃんと出す
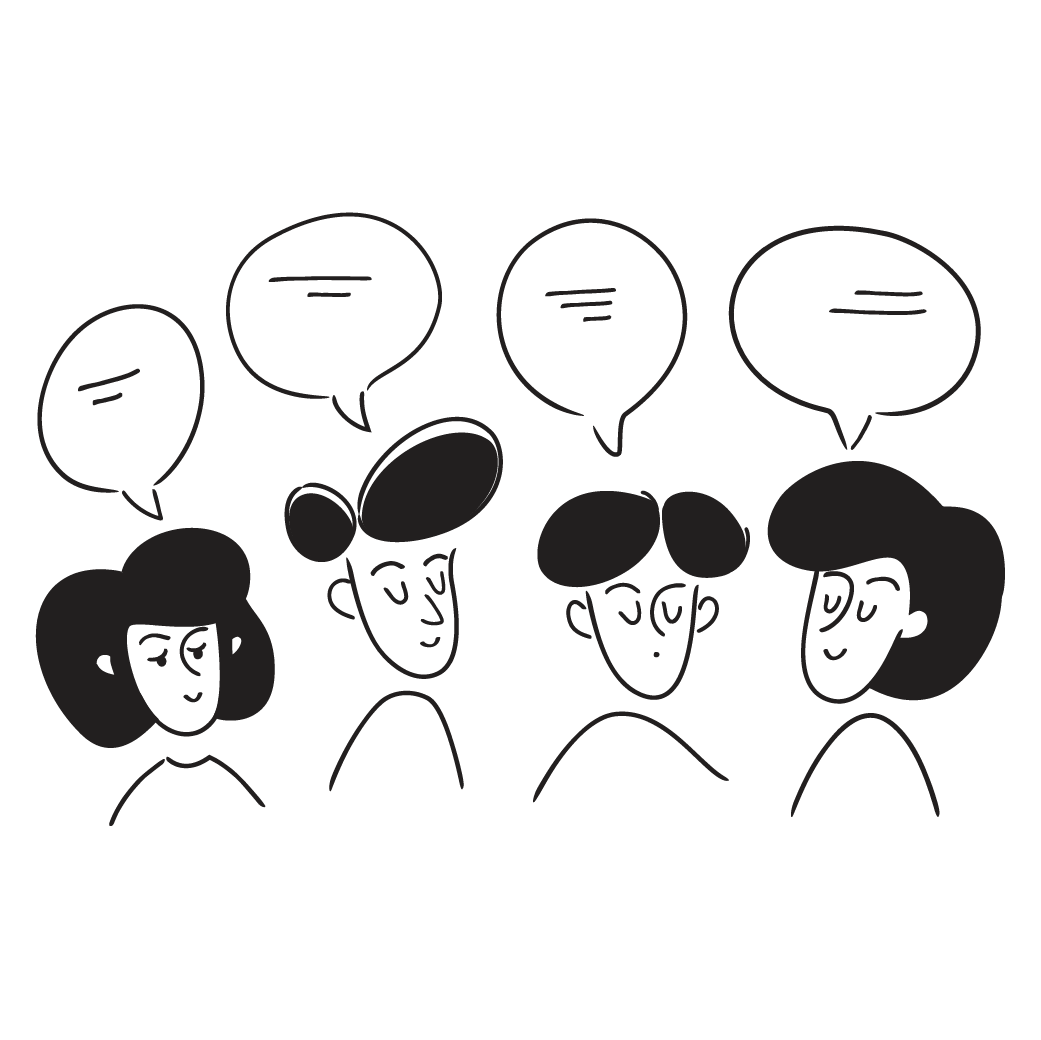
評価方法と割合:評価の割合(確認)
- 授業の感想:30%
- ブックカード:30%
- 学期末振り返りレポート:10%
- プレゼンテーション:10%
- 受講態度:20%
授業の感想とブックカードについては、提出すれば、(ほぼ)自動的に加点します。未提出でいると、単位認定に必要な点数に達しませんので、気をつけて下さい
※授業には3分の2以上の出席を必要とします ※評価基準は、授業目標に準じます
グループワークの心理的安全性
重要 | 「この場では安心して意見を言える」という感覚が何より大切です
- グループワークで話したことは外に持ち出さない
- 相手の意見を批判しない(マウンティング行為を含む)
- グルームのメンバー全員が「つながり」を生む声かけを心がける(「◯◯さんはどう思いますか?」)
グループワークの心理的安全性
禁止 | マウンティング行為
- 知識ひけらかし型:「この本は原著で読んでるから、翻訳はちょっとね」/ 「作者の別の論文を読んでないと本当の意味は分からないよ」
- 先取り型:「あー、この後の展開は◯◯だから、そこまで読まないと面白さはわからないよ」/「私、もう続編も全部読んでるから」
- 比較優位型:「その感想は初心者っぽいね」 / 「自分はもっと難しい本を普段読んでるから、この本は物足りないかな」
- 発言の矮小化型:「その見方は浅いよ、本当はこう読むべきなんだ」 / 「その感想はよくあるけど、重要なのは別のところだよ」 / 「それってあなたの感想ですよね」
アイスブレイク:共通点グランドスラム
ルール
- お互いにコミュニケーションをとって、以下の4つのパターンの共通点(または相違点)を探そう
| パターン | 内容の説明 |
|---|---|
| ① 全員バラバラ | 4人全員がちがう |
| ② 3人が同じ | 1人だけちがう |
| ③ 2人ずつ同じ | 2対2に分かれる |
| ④ 全員同じ | 全員が共通している |
見た目の特徴など、コミュニケーションをとらなくてもわかるものは避けて下さい
- 制限時間:10分
ビブリオバトル:好きな本を紹介しよう②
司会(タイムキーパー):ハート❤️︎️
本の紹介:5分(最低4分30秒は話すこと)
質疑応答:3分(しっかり3分間、質疑応答すること)
アフターセッション:5分(しっかり5分間話し合うこと)
- グループチャンプ本を決めて下さい
- 配布するカードに、日付、グループチャンプ本のタイトル、その受講生の名前、簡単な理由を書いて提出して下さい
- 残りの時間は、ブックカードのまとめ方、質疑応答の続きなど、各グループで有効に活用して下さい
Ⅲ. グループチャンプ本プレゼンテーション
グループチャンプ本プレゼンテーション
司会(タイムキーパー):ジョーカー🃏
本の紹介:5分(最低4分30秒は話すこと)
質疑応答:3分(しっかり3分間、質疑応答すること)
- プレゼンテーションシート
- 最終授業日に「クラスチャンプ本」を投票で決めます。忘れないためにメモを取っておいて下さい
- プレゼンテーションシートは回収しません
Ⅳ. 次回の授業と宿題
次回の授業と宿題
次回
- 研究分野の本を紹介しよう 第1ラウンド
宿題
- 授業の感想
- 締め切り:授業と同じ週の金曜日23時59分
- 研究分野の本についてのブックカード
- 締め切り:10月29日授業開始前